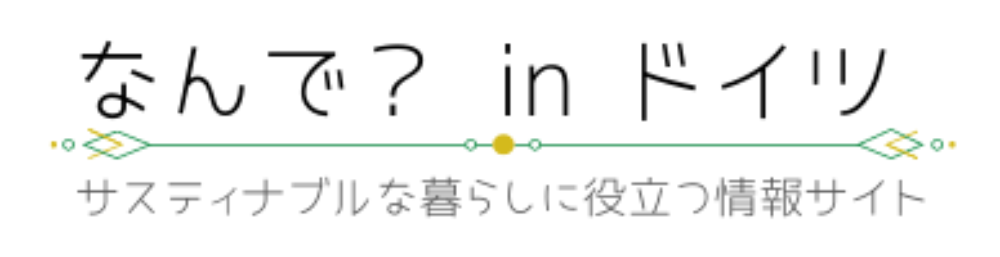公開日 2021年4月22日 最終更新日 2023年12月27日
あなたが健康な身体を維持するためにエネルギーは必要で、水分を摂り食事をして、最低限の運動を行いますよね。
エネルギーは自然に蓄えられるものではなく、何かの力を利用してエネルギーは創り出されます。そこで再生可能エネルギーという言葉からあなたは何を連想しますか?
この記事では生活に欠かせないエネルギーを利用する上で環境に負担をかけないように生活をするにはどうすればいいのか5つのポイントをまとめています。
もくじ
持続可能(サスティナブル)なエネルギー

生産されたエネルギーを使い過ぎず環境を守るにはあなたが消費する時にちょっとだけ気を付ければ節約できます。
- エネルギー(水・電気・ガスなど)は節約するよう心掛ける
- パソコンやテレビなどのスリープモードを避ける
- 洗濯機や食器洗浄機は低い温度を選ぶ
- 省エネの商品を選ぶ
- 再生可能エネルギーを選ぶ
節約が環境保護につながる
あなたは節水・節電を心がけていますか?目的は環境保護でなくとも節約をするためである人も多いかと思います。目的が何であれ、それがもたらす結果は同じで節約目的が環境保護につながっているのも事実なのです。
しかし、なんで環境を保護する上でその節水・節電が大切なのか?ともう一歩踏み込んで、疑問を持つことが今現在求められています。最近のニュースでも、異例の寒さ・暑さの報道が世界中あちこちでされていますよね。気候変動です。
未来も最低限数十年前のような暮らしを保つためには1人1人の環境保護のための行動は必要不可欠なのです。
洗濯機・食器洗浄機は低い温度を選ぶ
ドイツのWaschmaschine(洗濯機)は、温度設定があって最大90℃まで設定可能なので、なるべく低い温度で洗うと節電につながります。
洗剤も日本のように除菌剤が入ったものが普通ではないので、洗濯時の水温をあげて除菌するので、殺菌が必要ないようなものを洗う時には低温で電力を抑えて洗濯することができるわけです。
ドイツ生まれの【Frosch】フロッシュはエコで安全!環境と人にやさしい洗濯
しかし除菌するためにそこまで高温で衣類を洗えば、その衣類は低温で洗うよりも傷みます。これを防ぐのが日本でスタンダードになっている洗剤。高温殺菌同等の効果を化学製品を使って求めるのだから、自身や大切な人の身体を守るためには普段使っている洗剤を見直すことも大切かもしれません。
省エネの商品を選ぶ
今や様々な企業が省エネルギーを掲げた商品を売り出していますよね。便利さ・デザインなどとともに「省エネ」であることは商品選びにおいてとても重要なポイントにもなっています。
ドイツではEnergielabel(エネルギーラベル)というラベルがほとんどの主要な家電についていて、それを目安にどれだけ省エネであるのかが簡単に判断できるようになっています。
- 寿命が長く消費電力が少ないLEDを選ぶ
- 洗い物(水道を使うときは)をするときは水を止める
- 待機電力を使っているところは使用時以外電源を切る
再生可能エネルギーを選ぶ
エネルギーを大きく分けると、私たちが便利な生活に必要なエネルギーは限りある資源を使って生産されるエネルギーか、不要になったものを使ったり、自然の力を利用する自然(再生可能)エネルギーの2つがあります。
日本のエネルギー事情
日本は国内エネルギー自給率は10年前(2010年)の20,3%から、2012年には10%を切り、2017年には9,6%まで下がっているのです。つまり、その他の約90%のエネルギーは日本国外に依存しているということになります。(参考:2019 日本が抱えているエネルギー問題)
エネルギー自給と再生可能エネルギー
ドイツのエネルギー自給率は36,9%日本は9,6%(2017年)という数字から、いかに日本のエネルギー自給率が低いかは明らかですよね。実際にエネルギー自給に欠かせない再生可能エネルギーはどんなものがあるのかご存知ですか?
- 太陽光
- 風力
- 水力
- 地熱
- バイオマス
わが家も今の家への引っ越し後、太陽光発電の会社と契約をして電力をもらうようにしました。会社を選ぶときも自然を第一に考えた会社方針など、本当にそれが環境保護につながっているのかという疑問を持ちながら、幾つかの会社を吟味しました。化石燃料という限りある資源に頼らないエネルギー供給を選択することは、地球・環境を守る第一歩へと繋がります。
しかし化石燃料エネルギーと比べると、再生可能エネルギーはコストが多少かさむところから、やはり電力コストを減らすことも大きな課題の1つになっているわけです。
原子力発電
日本という島国は地震や台風などの自然災害が比較的多い国で、地形的に原子力発電に不向きと言われています。しかしながら広大な土地があるわけでもないので、さらに多くの再生可能エネルギーを作り出すことも難しいのが現状です。
2011年に起こった東日本大震災を境に、もちろん原子力発電の割合は減っていますが、使用済み燃料のタンクがいっぱいになってきている今、海の水中へ、蒸発させ大気中へ流すかを検討しているという記事を読みました。👉2020年10月に海へと流す決断がなされました。
日本の原発以外のエネルギー資源
国内エネルギーの自給率が約20%(2010年)から、約10%(2017年)まで減ってしまったわけですが、それは言うまでもなく原子力発電によるエネルギー供給が減ってしまったからではありますが、現在それの代わりになっている資源は一体なにかというと、主に以下の3つです。
- 石油
- 石炭
- 天然ガス(LNG)
エネルギー資源は海外から輸入
これらの資源は、サウジアラビアやオーストラリアをはじめとする、外国から97%以上が輸入されています。ということは、国際情勢が変わり支給がストップした時にはその代わりになるものが必要になります。(2017年石油・石炭の化石燃料依存度は87,4%)
またこれらの化石燃料などは、温室効果ガス(GHG)を多く排出するため、化石燃料を使えばつかうほど、地球温暖化へとつながることも問題視されています。(2013年のピーク以降2017年には排出量が少し減っている)
日本の掲げる3E+Sとは?
安全性(Safety)を大前提に、自給率を上げ(Energy Security)電力コストを減らして(Economic Effciency)温室効果ガス排出量を減らすこと(Environment)を3E+Sと2030年に向けての目標達成のため掲げているようですが、最近起こった水災のことも考えると安全性を守ることは日本にとってかなり大きな問題であり課題であるのはいうまでもありません。
グリーンピースの署名活動
グリーンピースの署名活動
グリーンピース(英:Greenpeace)は、39か国以上に拠点を置く非政府の自然保護団体。(引用:Wikipedia.jp)
現在グリーンピースが、政府の掲げる2050年までに原発を稼働させながら二酸化炭素の排出量を実質0にする目標を改め、自然エネルギーのみのエネルギー政策を求める署名を行っています。